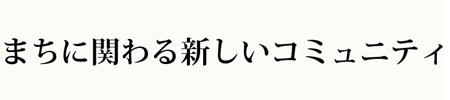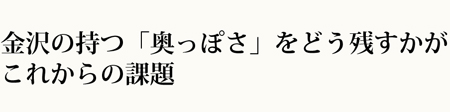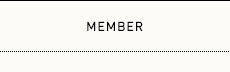■プロフィール

内田 奈芳美 埼玉大学 人文社会学研究科 准教授
福井市出身。ワシントン大学修士課程修了、早稲田大学理工学研究科博士課程修了。博士(工学)。専門:都市計画・まちづくり。金沢工業大学環境・建築学部講師などを経て、現職。 |
-----先生は福井市出身で、首都圏やアメリカにも在住され、金沢工業大学に赴任されました。金沢に来られる前と後の印象はどうでしたでしょうか?大きな違いはありましたか?
子供の頃は訳あって金沢にはよく来ていました。原風景として近江町市場だけはっきりと覚えています。あとは金沢大学。お城の中にある学校として憧れはありました。当時は近江町市場も整備される前で金沢21世紀美術館もなく、ひがし茶屋街も親が連れていくような場所ではありませんでした。
-----今のような重要伝統的建造物群保存地区(重伝建)の整備がされる前ですね。ひがし茶屋街は過去に火災があってそれを機に直さなければならないということで経済人たちが立ち上がったように思います。重伝建の運動がなければ今頃は廃れてなかったかもしれないですね。
昔の写真を見ると塗装はアスファルトで昼間に空いている店も少なかったようです。そう思うと重伝建の運動は大切だったと思います。
-----大学で東京やワシントンにも在住され各地方都市もお仕事で行かれているなかで、それらの都市と今の金沢を比べたときに金沢の特徴とは何だと思いますか?
金沢は魅力的だと思うのですが、それは背後にあるストーリーを知っているからだと思います。逆に裏のストーリーを知らない人が金沢をどう思っているのかは気になるところです。来たばかりの頃はどうしよう、何もないと正直思いました。でもよく見てみると豊かなストーリーがあることに気づきました。
-----新幹線開業後の今の金沢の現象についてどう思われますか?
金沢に来られている人は多いですが、まちの本当の魅力やストーリーについて理解していない人が多いように思います。
-----具体的にストーリーを見せていく際の方法やプロセスは何があると思いますか?
点と点でしか移動しないというところに課題があると思っています。本当は普通の人が住んでいる普通の道の方が面白く、例えば明治時代に建てられた町家や、戦後すぐの状態を感じる朽ちて残っている場所などに「時間断層」が見えてきて面白いと感じます。
-----日本の観光はどうしても点で見るところがありますね。ひがし茶屋街も外観保存はされていますが内部はそのままのものもあれば現代的にアレンジしたものもある。また、一歩メインストリートを外れると、古い町家の外観を嫌って金属板で囲ってみたり、現代的な建物が混在してたり。まちの過程を見ていくとそれ自体も面白いと思います。
そのためには見る側にもリテラシーが必要で、ブラタモリを面白がる人がいるように、ああいう見方ができるということを来る側も学ぶ機会が必要だと思いますね。凍結したまちではなく、断層がある方が実は面白いのではないでしょうか。
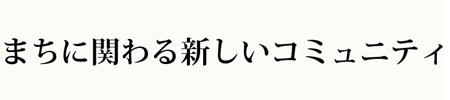
-----内田先生はまちづくりとコミュニティの話もよくされますが、私や内田先生が所属しているNPO法人趣都金澤をもとにお伺いしたいと思います。趣都金澤のように今までの地縁とは異なるコミュニティが街に加わり始めていますが、それと今後のまちづくりはどう繋がりあっていくと思いますか?趣都金澤は割に独自性の高い目的型コミュニティだと思いますが、今後の継承なども見据えながらシステムとして街にどう落とし込んでいけるのかが課題と感じています。
これまでの地縁型、目的型とは異なる第三のコミュニティとして「プラットフォーム型」という単一目的ではなく明確な目的がはっきりしないコミュニティがあってもいいと私は思います。例えば、これまでの日本は縦型社会で企業に属するということが自分のコミュニティとして非常に重要でしたが、日本人は実はイメージと違って個人主義でかつ交わりがたいという人たちが世界と比較した傾向として調査で出てきています。新しい日本人の型として、従来の家族や会社といった縦型の繋がりとは別に、目的はないけれども繋がりあう横型のプラットフォーム型のようなものが出てきているというのが新しい動きで、価値観が変わってきているところだと思います。
-----個人主義を具体的に言うと?
他人と関わりたがらない、自分の属しているところだけで完結させようとする傾向があります。もちろんアメリカのようなところだと異なるコミュニティのぶつかり合いも激しいので、横の繋がりがないと衝突し合うという面もあるのでそれに比べて日本は安心して個人主義でいられるところがあります。
-----確かに、日本はまぁまぁという中間領域があって、無理やりにでも「和」の方向にもっていく傾向にありますね。
日本人が安心してディティールにこだわれるのは島国で敵が攻めてこないからだと、千利休についての本を読んだときそういった記述がありました。やはり囲まれた範囲のなかで安心していられるというのは、敵がこなかったからが大きいと思います。
-----今は日本でもSNS等の発達も含め個と個の対立が強くなっていますね。普通、多くの目的型コミュニティは年齢や職種などにより割と囲いこもうとする団体が多く見受けられます。しかし、NPO法人趣都金澤は年齢や職種にも幅があって、それをどう柔らかく受け止めていけるかが、このような対立が際立つ時代、そして高齢化時代だからこそ問われているようにも感じます。
特定の年齢層だけが集まってパラダイスを作ろうとしてもだいたいは上手くいきません。コミュニティやまちづくりについては独自性の高さは良い事と悪い事の表裏一体で、独自性があれば特定の目的がなくとも人は集ってきて柔らかくまとまりはしますが、独自性が高いゆえに継続性がないという話はよく聞きます。
-----難しいところとして無理やり目的を重ねようとすると先ほど話した柔らかさが削れてしまいます。もし新しいプラットフォーム型のようなコミュニティが必要だとすると、それを今度はどのような形で育て継続させていくのかが新しい課題だと思ったりしました。
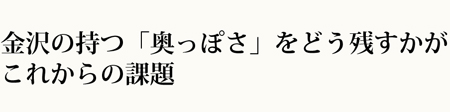
-----新幹線が開業し観光客が流れてきている一方で、金沢21世紀美術館やひがし茶屋街、近江町市場など歴史的な文脈を読み取りながら丁寧につくってきたものが評価されてきた状況もあり、他の地方都市にはない一通りの基礎的な土台が出来てきたように思います。新幹線時代を迎えて次の金沢に期待すること、また東京と金沢についてどのように思っていらっしゃいますか?
新幹線は来ましたが、金沢は「奥っぽさ」を失わないでほしいと思います。金沢は奥であったことの意味があって、知る人ぞ知るという神秘性があると思います。住んでいる人はそんなことは思って生活しているわけではありませんが。「奥」という概念は日本的な空間の考え方であって、イタリアの研究者も空間の奥行きについて「ここ・向こう」という概念を言っていましたが、「奥」とは言いません。「奥」とは、私がいるところは「ここ」だが、さらに奥に何かを期待させる場所があるということです。要は壁で覆われているのではなく壁に穴が空いている状態で、日本での障子のようなイメージです。少しは見えますが何があるかは分かりません。
-----チラリズム的な?
俗っぽく言えばそうですね。存在性を、神秘性を守らないといけないと思います。奥っぽさには、日本の時間と空間の読み取り方が関係していると思います。
-----「奥っぽさ」というワード、気になりますね。まだまだお話しを伺いたいところですが、本日はお時間が来ましたのでここまでで。続きは次回のお楽しみに!内田先生、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
次回、テーマ「奥っぽさから」に続く (インタビュー実施 2016年2月16日)
■インタビュアー

浦 淳 (株)浦建築研究所 代表取締役 / NPO法人趣都金澤 理事長
1966年金沢市生まれ。大阪の大手建設会社を経て浦建築研究所に入社、2006年代表取締役に就任。NPO法人趣都金澤〔理事長〕、日心企画(大連)有限公司〔執行董事〕、(株)ノエチカ〔代表取締役主宰〕など兼務。建築設計や企画デザイン・各種コーディネート事業を通じて、北陸の建築・文化の世界発信を目指す。 |
「きょうの現代美術」
ウォルターデマリアの「ライトニングフィールド」の背景を探りたい。この作品は、ランドアート、環境芸術という括りに入る。同じカテゴリーに入る作品でも、作家の資質によって大きく作品の在り方は異なるが、この手の作品の多くは、身体感覚に重きを置いて制作されている。
作家の身体感覚である。それが体一つで作り出すという感覚の場合もあれば、大掛かりな土木作業を思わせるタイプもある。例えば前者は、リチャードロング、アンディゴールドワージィー。後者は、マイケルハイザー、ロバートスミッソンだ。
ここまできて、すでに気づいているかもしれないが、身体規模感覚の捉え方や哲学の違いは、作家個人というよりも、その作家の属する文化、文明における自然観が影響しているようだ。ロングは英国人だが、散歩をする、歩くということがベースになっており、自然に対して人為的に変更を与えることを抑える傾向にある。一方、ハイザーはアメリカ人であり、まるでな土木工事のように大掛かりに自然に働きかけるという具合に、2つを比べると力の表現と自然観がまるで異なっている。裏を返せば人間観(身体的規模や能力の感覚)の違いである。
冒頭でも書いたが、この一見2つの異なるタイプのランドアートは、その成り立ちにおいて根本は同じである。それはどちらも身体感覚に準じた表現であり、スケールや哲学の違いはあっても、一人の人間という視点によって成立しているのである。だから一見複雑に見える作品だが、実は、大地あるいは自然に向き合う人間という構図で作品を理解すれば、案外わかりやすい。つまり《自然vs人為》という構造で作品化されている。多くのランドアート、環境芸術は、この《自然vs人為》という構図で理解でき、その対応関係の文化的異なりのバリエーションとして理解できる。あるいは自然をどのように考えるか、という自然観の違いと言ってもいい。
ところが、ウォルターデマリアはこのような構図からでは理解できない。つまり作品の構造が人間の行動や人間が自然をどのように道徳的、哲学的に見るか、いう視点から接近しても理解できない。《自然vs人為》という構図ではないのだ。(続く)
「きょうの現代美術」は、何回目になるのかな? またデマリア。彼を世界的に有名にした作品が「ライトニングフィールド(カミナリの高原)」。これはいくつかの点で、それまでの美術と異なっていた。
まず、美術館に展示されないこと。また移動できないこと。自然の中にあること。またスケールが大きいこと。そしてこれらの特徴を持った結果、どこからどこまでが作品かがわからなくなってしまったこと。つまりこれまでの絵画や彫刻のように、ひとつの物として視界に収まるわけでも、作品として完結するわけでもないものが生まれた。そしてそれが、ただ自然の中に広がっているという光景を作り出してしまった。
今われわれは、こういう作品をインスタレーションと呼んだり、サイトスペシフィックアート(その場所に根ざしたアート)と呼んだりする。或いは、環境芸術、アースワーク、ランドアートという呼び名を聞いたことのある人もいるだろう。デマリアの始めた仕事(ほぼ同時にマイケルハイザー、ロバートスミッソンが60年後半から自然の中で作品制作。その後、クリスト、タレルなどが続く)が、これらの新しい美術動向のほぼ始まりである。その頂点であり、記念碑的作品が1977年の「ライトニングフィールド」ということになる。これ以降、作品は美術史から徐々に自由となり、場所、環境や歴史と関わり、様々な文脈(例えば社会学、人類学、文明史など)と結びつく。
環境芸術や自然を使ったアートを紹介するときに必ず登場する「ライトニングフィールド」だが、果たしてどれだけの人が、実際にそれを見たかは疑わしい(本当は作品スケールから『体験』と言った方がいいが)。なぜなら、人がたやすくいけない遠隔地にあり、かつそこに行くまでがとても面倒だからだ。UFOが出ると言った噂が登ってもおかしくないほどの人里離れた場所にある。ニューメキシコ州の都市アルバカーキからインターステイツというアメリカ版の高速道路を車で数時間ほど、ひた走り、それを降り、また下道を走る。数時間、人も車もほとんど見ることのない。砂漠地帯に張り付いたような舗装道路を走る。道の脇に家がまばらに現れる。町と考えていいのか、どうなのか迷っているうちに、ほとんどの人が通り過ぎるこの場所が終着地クマドーだ。
「ライトニングフィールド」に行くには、さらにここから奥に行かねばならない。まずはここで乗ってきた車を捨て、ライトニングフィールドを管理する地元のカウボーイの車(もちろんゴッツイ四輪駆動車)に乗って、今度は舗装のない凸凹の道を行く。地元カウボーイの運転は意外に紳士的だが、それでも体は大きく上下する。行けども行けども目的地に着かない。
そもそも視界を遮る物のない場所だが、さらにその視界が開けてくると目的地は近い。視界が360度広がる平原である。影すらできない平らな土地にポツンと頼りない木造の小屋が蹲るように存在する。地面からの突起物はこの小屋と遠くの井戸だけである。デマリアは、作品設置の条件といて可能な限り自然地形で平らな場所を探したにちがいない。
小屋は一泊するための場所だ。カウボーイは私たちを下ろすと小屋での過ごし方と緊急時の連絡の取り方(一つ、黒電話があるだけ)を伝えて、去って行く。滞在者だけ残る。
少し離れたところに給水施設。こういうものがあるととりあえずは、すこしほっとする。それぐらい人気のない場所なのだ。周りには丈の低い半ば干からびたような草がただ広がるだけである。その先にはデマリアがこれ以上の精度は出せないというほど精巧に作ったステンレス製の柱が立っている。これだけがとっても異質だ。広大な砂漠に縦横の一辺が1キロと1マイルの四角形が想定され、400本の柱が規則正しく立っている。
こんな場所に身を置いていると「私は今世界の果てにいる」のではないかとぼんやりと思うのだ。
「ライトニングフィールド」はそんなところにある。小屋は最大でも十人に満たない人間しか泊まれず、そこで一夜を過ごして、ライトニングフィールドを見る。陽の高いうちはほとんど存在に気がつかないステンレス柱が、日没と日の出の時間だけくっきりとした陰影を持って現れる。光が横から当たるためだ。
厳しい自然環境の中にあるため、ここに入れる季節は限られている。冬場の状態がきびしいときは、人は近付けないから、多くても年間千人にも満たない人しかここを訪れることはできないし、実物の作品を見ることもできない。それでも作品は有名である。現代美術をかじっている人間であればどんなものか、皆、知っている。ランドアートの代名詞と化したこの作品は、20世紀後半を飾る名作として美術書に頻繁に登場してきたからだ。画一したイメージはその過程で生まれた。使われる写真はいつもきまって、カミナリが落ちる写真である。ステンレス製の柱に無慈悲にもカミナリが落ちているというものだ。それが現実の落雷とは別に人々の心に映像化し、イメージとしてこびりついてきた。イメージの独り歩きという現象も、メディアの発達した今日の出来事だ(そしてそこで記号的に意味が語られる)。だが、それとは別に生な体験が、訪問者の中で形成されて行ってもいるのだ。果たしてポップアートさながらに一人歩きし、増幅する記号的イメージのライトニングフィールドか、それとも、ここの訪問者のうちに残る経験としてのライトニングフィールドか、どちらがデマリアの伝えたかったことなのだろうか? くっきりと意味を語る映像イメージに反して、個人に残る体験は、あまりにも頼りなく、モワモワしたものなのである。
しつこくデマリアの第5弾かな?
今日は、「ハイエナジーバー」についてです。この作品も1960年代半ばの初期の作品です。これはタイトルに素直にデマリアのものの考え方が出てます。つまりこのステンレスバーは、エネルギーを持ってますよ、ということだ。デマリアは、
ものには質量があり、重力があると考えていて、それを作品化している。そういう意味では「ハイエナジーバー」も「ボールドロップ」も同じテーマである。さて、そこで終わる作品ならば、「ボールドロップ」の展開版ぐらいの話で終わる。ところが「ハイエナジーバー」の主要なテーマはそこだけではない。むしろ作品の市場性と芸術の問題に神経が向いている。まずこの作品の販売価格は、1万ドルである。価格の高低が問題ではない、価格が変わらないということがポイントなのだ。転売時も変わらない。何度売っても同じなのだ。つまりこの作品の市場性は変わらない。いやその言い方は正確ではないなあ。「ハイエナジーバー」だけ価格が変化しない。芸術性と市場評価が連動していないのだ。デマリアはもうひとつ仕掛けをしていて、この作品は、何本でも制作できる。実際に何本か存在する。
つまりこれは、芸術の市場性とオリジナルに関する作品だ。
デマリアがこの作品を作って、半世紀になる。デマリアも数年前に亡くなった。現代美術をめぐる環境も異なっている。近年、他の作品とに混ざってハイエナジーバーもオークションに出てくる。そこでの落札結果は、デマリア決めた価格などお構いなしにすごい数字で取引される。作品には証明書がつく。そこには、購入者が転売する場合の条件も書かれており、決して購入時の値段一万ドルを越えたり、下回ったりしてはいけないというルールだ。しかしそんな条件を守る人はいない。みんなが現代美術の市場性とパワーに酔いしれている。
「今日の現代美術」というタイトルでエッセイを書こうと思っていましたが、タイトルをよく考えると「いま」という形容がダブっているんだよね。それに本人は「今日の」を「きょうの」と読んだつもりが、「こんにちの」とも読めるということに気付いて、この二つではだいぶ伝わる雰囲気が違うので(「こんにち」は堅い)、「きょうの現代美術」と開くことにしました。「きょうの料理」とか、そんなフランクさですね。
しつこいが今日もデマリアの球体作品です。追記ですね。木製の「ボールドロップ」という作品が1961年の製作で、ニュートンのリンゴの話よろしく、重力について触れた作品です。重い球を上から落とすと「ゴン!」と床にぶつかる、という身も蓋もない作品。まさに落下を知ることになる。それが40数年後に直島にあるような巨大な球体のインスタレーションになるという話をしました。その間には、水平に移動する球体作品があり、円などの幾何形態から、十字架などのシンボリックな形まであり、重力、引力といったエネルギーを持つものが、ある形を与えれられて、それをなぞるように移動する、そして、それが歴史や人間の作り出した理念といったものに触れているのではないか、という話を前に書きました。実は書きながら、垂直の重力をテーマにする作品から水平にそれが展開し、幾何形態に沿って移動する作品までには、コンセプト的な開きがある、アイデアの飛躍があるなあと思っていたのですが、やはり間を埋める作品がありました。単に球体が水平に移動する作品で、かつ、垂直型の作品のときに重要な要素であった落下音「ゴン!(これは重力を感じさせるという意味で重要)」を引き継いだものなのですよ。 私はこの作品を実見していないので、想像するしかないのですが、金属棒に溝が掘ってあり(トイのように)、そこに球が入っていて、自由に動くようになっている。ただ自由といっても、直線に沿ってなので、それほど形態としては目を引くところがあるわけではないのですが、興味深いのは、集音器や音の増幅装置が付いており、球が移動し、あるいは壁にぶつかった時の衝撃音を何らかの形で加工して音として出していたのではないかと思わせるのです。つまり音を作品の一部にしていたということです。これはとても興味深いポイントで、音について、実は直島の「タイム、タイムレス、ノータイム」という作品でも使用されているのです。ときおり「ゴン!」という音が室内に響きます。デマリアは、61年製の「ドロップボール」という作品から単に球体という形態だけを発展させ、作品として展開しただけではなく、初期から興味を持つ、そして自分の芸術活動の始まりでもある音楽(音)を継続してずっと問題にしていたことになります。前から感じていましたが、デマリアは、音や時間、環境というものに対して敏感に反応してきました。造形的に非常にきっちりとした形態を作り出す作家なので、空間的な美しさに配慮した視覚重視の造形作家のように見えてしまいますが、実は極めてコンセプチュアルであるばかりか、ミュージック、ハプニングなど、こういった時間的、非形態的な要素に強く反応する作家でもあるのです。その証拠に、実は彼は、当初美術作家を志していたというよりも、音楽家を目指していました。小学校時代から小太鼓をやっていましたし、パーカッション、ドラマーとして、ルーリードらとともにベルベットアンダーグラウンドの前身の実験的なロックバント「ドラッズ」にも所属していました。当時のデマリアの活動を知ることができる貴重なCDがあります。そこでは彼はコオロギとドラムセッションをし、海岸に打ち寄せる波とドラムセッションしていました。ある意味では、視覚芸術家としてのデマリア以上に音楽家としての彼のほうが年期が入っていると言えるほどなのです。というか、デマリアにとっては、音も視覚も分けられるものではないのかもしれません。さて話を進めて、この作品を制作していたこの頃、つまり1965、6年頃ですが、もうひとつ興味深い作品を作っています。「ハイエナジーバー(高エネルギー柱)」という作品です。これは単なるステンレススチールのバーに見える作品です。これを立てればまさに2001年宇宙の旅のモノリスです。文字が書き込まれていて、何本か制作しています。これもまた別の意味で興味深い作品ですが、今日は、直線に溝が切ってあり、そこに球がはめ込まれている作品との形態的な相似だけに触れてこの話を終わりにします。「ハイエナジーバー」にはまた別のストーリーがあります。それは芸術性についてオリジナルと価格から考えさせる作品です。これついてはまた次の機会に。
「今日の現代美術3」という名前をつけました。前の二回もカウントして3回目の投稿。もう勝手にシリーズ化しよう! デマリアの球体好きの別バージョンです。こちらは球体が動くというだけでなく、それが支持する形態が意味を持ちます。例えば丸三角四角があり、また十数面体というものもあります。それに単なる幾何形態ではなく限りなく象徴的な意味を帯びた形もあります。例えばクロス十字架。これは明らかにキリスト教との関連を示すものですし、それに卍ハーケンクロイツなども使用しています。今ではナチスドイツの忌まわしい歴史を象徴する記号になってしまいましたが、これらは歴史的にも古く、世界各地に存在する重要な記号です。球体は固定されていないから、形や記号をトレースするように動くだろうと想像させます。実際に観客によって動かすことはできないから想像になりますが、それを裏付けるように球体が動いた跡が見て取れる。初期の木製箱型作品では垂直にストンと落ちる姿によって、重力を表していた球体ですが、今ではある記号や形をトレースしながら動いていき、その背後の意味や歴史を掘り起こしていく、解釈やイメージを形成する力を表しているものに見えます。さてもう1つ、デマリアが単に幾何学を用いているわけではないということがよくわかる参照作品を紹介します。日本の禅僧である仙厓の丸三角四角の作品です。これを見ると「ああ、なんだ!デマリアはこれを参照したのか」と納得できます。デマリアは単なる抽象彫刻家ではありません。非常にコンセプチュアルに作品を制作し、何重にも意味を重ねています。ですから仙厓の作品もただの形態的なアイデアと参考にしたのではなくて、はっきりと思想的な背景を理解して引用しています。そこが面白いところですね。抽象幾何形態だけでなく、象徴的な意味をふんだんに持つものを用いることで、おおっ!重力が歴史や宗教的な概念や人間が作り出す想念にも関わってくるのかと空想させる魅力があります。つまり力が世界を動かしているのか、ということです。ここまでくるとデマリアの想像力が飛び跳ねている感じですね!
前回、現代美術家のウォルターデマリアの作品を紹介したら、いいリアクションだったので、調子に乗って作品紹介。デマリアの球体への興味の話の続きです。前回、直島の作品から急に球体が出てきたと思ったが、実はそうではなく、三角四角などの他の直線的な多角形と同様によく使う形だったという話。デマリアの重要なモチーフでした。今日はその証拠となる初期の作品を紹介します。身長ほどある木製の箱に縦にちょうど手が入るほどの穴が二つ空いています。備え付けの球があり、穴に入れることができるようになってます。上から球を入れるとそのままなんの抵抗もなく、下までゴン!と落ちます。まさに間髪入れず「ゴン!」です。すごい音がして「はっ!?」として、気まずい感じになります。木製の箱に対して、球体も硬い素材ので、それで結構な衝撃なります。この作品は、この気まずい行為、つまり、「ゴン!」と石の球を落とす行為が鑑賞体験になります。さてこれによってデマリアは何を伝えようとしたのでしょうか? 「ゴン!」という強い衝撃を感じて気まずい気分になるというところの前半部分だけが大事なので、そこを考えてみましょう。後半の「気まずい気分」は、私が勝手に感じているだけで重要でもなんでもありません。あくまでポイントは前半の「ゴン!」という衝撃音から想像できることです。重い物が落ちてきたなあ、あるいは私が驚いたように想像以上に「重い」物が落ちてきたという印象を与えたいのでしょう。本人は語っていないのですが、想像するに、たぶん、「重さ」の表現をしたかったのではないかと思います。当たり前ですが、物はどんなものでも重さがあります。重さはどんなものでも例外なく存在します。そしてそれは、どこまでも広げることができる、モノを司る法則でもあります。つまりものである以上失うことのない「重力」が存在するのです。木製の箱に不釣り合いな重い球。四角く空いた窓から石を入れれば、瞬時に下の窓まで落ちます。その速度は「こんなに早いのか!」と思うほどの瞬間です。「ゴン‼︎」です。デマリアといえば、何か動かない普遍的なコンセプトのイメージがありますが、むしろこのように動きの中に見るべきものがあるのかもしれません。例えば、代表作のライトニングフィールドも同様です。突然、雷が参入し、落ちる。音への興味は、彼のキャリアの始まりが音楽家だったということからもわかります。この作品は、デマリアが気に入っていたようで、スタジオにずっと置いていました。私もスタジオで「ゴン」をやってます。たぶん作品制作年は1960年代のものです。かなり早い時期のコンセプチュアルアートですね。モノリス型の箱中央あたりに四角の中に丸い玉が見えるのがわかりますか?あれを持って上の穴から落とします。「ゴン!」さてこの球は、40年後には2メートルを超える不動の球体として直島に登場します。
今日は、自分の好きな作家のまだ見たことのない作品をあげよう。ウォルター・デ・マリアの作品。ドイツにあります。直島の作品の姉妹作品。こちらの方がちょっと大きい。直島は濃いグレーですが、こちらはちょっと赤い。デ・マリアが生きている時に産地を聞いたが、忘れてしまった。作品の順番は直島が先です。直島当時は、いつも直線的な幾何形態を使うデ・マリアにしては、球を使ったのが唐突に思えた。ちょっと作品としてどうなのだろう?と不安になったりして。
しかし
全然そんなことはないね。後期の傑作というところだね。最近になって当時の印象は間違ってたなと思っていて、これまでの作品を振り返ると初期から球体を使ったものは多く、むしろ頻繁に使用していると感じる。ただあの時そう思えなかったのは、私の不注意もあるけど、デ・マリアはあれほど全面に球体を出したことがなかったらなんだと思う。その後この球体での展開は晩年の主要なシリーズになった。当時、スタジオには球体がたくさんあった。そういえば、その変電所跡のスタジオも売却されてた。
ニューヨークのマンハッタンだったので、すごい値段だった。
いつもミルフィーユと聞くと金沢のことを想う。
30年余りも前のことだ。
今と違って甘いものを食べなかった頃、誘われミルフーユケーキなるものを食することとなった。
初めて見るミルフィーユは、パイ生地・チョコレートの薄板・
生クリームにフルーツ・スポンジと様々に層をなして、綺麗で美味しそう。
どこから手をつけてよいのやら、、、、。
案の定、グチャグチャに散らかし食べ終えた。
美味しかったのだろうが、味はさっぱり覚えていない。
只々、食べにくい思い出が残った。
そして《金沢》みたいだと その時思った。
建築家の水野一郎先生が、金沢はバームクーヘン都市と表現されていると最近知り、
きっと同じように思っておられるのだと思うと嬉しく光栄だ。
ミルフィーユ。 美味しさが層をなしている。味は食べてのお楽しみ。
どう食べようかで味も変わろうというもの。
チョコやパイ、各層その下は横から見るしかない。
味を思い描きつつフォークを縦に入れると、堅めのパイやチョコレートが下の柔らかいクリームなどを押し出して
綺麗だったはずのその層も台無しになる。
最初にみたミルフィーユは全部の層が違っていた。と思う。
今インターネットでミルフィーユの画像を探すと、割とシンプルで食べやすそうなミルフィーユが多くなっていて期待を外れたが、
それでも多種多様。あの食べにくそうなミルフィーユが今でも少し形を変えそんなに健在なのだ。
コアなファンも多いことがわかる。
最初に見たミルフィーユの画像に行き当たらないので、その道のプロ、同級生に尋ねると様々な情報を寄せてくれた。
流石!ありがとう‼︎
教えてくれた本場フランスのミルフィーユが思い出深いミルフィーユに一番近かった。
素材が活きている。
金沢のまち。
町の名も様々だ。
横山町・五十人町/尾張町・近江町/白銀町・大工町/寺町・春日町/銀杏町・地黄煎町/油車・六枚町・・
武家/商人/工人/寺社/自然、故事由来も名をあげればきりがない。
「旧町名ならだいたい場所の見当がつくのに、、。」仕事の使いが多い母の口癖だった。
歩いて廻るスケールの金沢の城下だが、海も近い、山も近い。
町から6km程直線に伸びる金石往還(藩政期造営)の先は日本海。ここはかつて銭屋五兵衛も活躍した北前船で栄えた金石町。
ここに1300年近く鎮座する大野湊神社の能舞台では神事能が400年程続いている。
隣の大野町は造り醤油で知られるが、両町共に古い町家が多く残っている。
金沢のまちのすぐ背には山も迫り竹藪も多く筍も美味しい。
山合いの町も多く、そのひとつ二俣町の和紙は1300年前を起源とし桂離宮松琴亭の襖や床に使われている。
青と白の加賀奉書が市松模様に貼られとてもモダンだ。
我家にも青白市松文様の入った襖がある。
もう45年を過ぎ随分すたれている。が、代える決心がつかない。
襖を新調した頃には、そういった襖紙をつくるひとも使うひともあまたあっただろう。
今のカタログには無い。
部屋と建主を見て建具屋さんが祖父や父と相談もせずに入れたように思う。
襖の胡桃の縁は全く年月を感じさせず、だんだんに美しく思う。

外から見えない金沢。
外に見せない金沢。
ひとも物も空間も多様。
道も路も未知。
オヤジギャグではないが、路にしかり、
芸道に入るにもチョコレートの薄板に阻まれて、先が見えないばかりか、壁が硬そうだ。
チョコばかりではない。パイ生地の薄い層といえど曲者顏で破壊力は相当にあり時に皿を飛び出してしまう。
見えているようで、見えてはいない。
《ひと》は実際に触って初めて見えていなかったことがわかる。
物や器は使われ淘汰される。
薄い層を根気よく剥がしていくと、綺麗な下の層にたどり着く。
ある時、コチッとチョコの薄板が気持ちよく割れ、下の生クリームやフルーツと美味しく味わえる。
チョコも熱にゆるむ。
だが、パイの剥がれた極薄い断片をひとつ食べてもパイ生地の美味しさには辿りつけない。
大胆に食べたいように食べて醍醐味となる。
慣れてくれば散らかることなく様々に楽しめよう。
見えない先、先を見ない繰り返しの中で、生まれてくる楽しみも味わい深い。
忽然と美しいものを目にした時の喜び。
忽然と真理に触れる畏敬。
客層は30才前後のある酒場でのこと。
カウンターに連れではないひとり一人が肩を連ねている。
「今年は寒くって、道もつるんつるんやし。、、、みんなお能みたいに歩いてたし。」
「そうそう、みんなお能の様やった」、、、、
「学校から必ずみんなお能を観に行ったし」
と4人程肩をよじらせ話している。
能の足の運びのように、腰を据え足を上げずの安定した歩き方で凍った雪の上をささと進む様子を言ったのだろうが、
凍った雪道からのお能の話しを、若いひとがグラスを傾けしている。
着物離れも進む中、街をゆくと若い方の着物姿も増えた。
新幹線での観光の中、レンタル着物で散策、お抹茶もという女子やカップルが増えたこともある。
少し前まで、およそ着物とは言いづらい光景もあったがしばらくの間にいい感じも増えてるように見える。
ミルフィーユにまた美味しい層が積まれつつある。
無邪気で新鮮な素材が重なってほしい。
金沢にはワンダーランド、
子ども心も大人ごころにも少なくなったが邂逅が今も残る。路もひとも道も。
冒険心とちょっとの勇気。
そして辛抱や根気というのもちょっとは入れたほうが滋味風味も深まるというものだ。

シルクロードの東端で文化を醸した日本のように、都に遠く都の風の吹き溜まりの根雪のようにうず高くに成し成された金沢。
魑魅魍魎に出会うのは滅相もないが、路地や木立の傍、座敷や蔵の奥から何か覗かれているような気がするくらいの
場が少しは在り続ける金沢であって欲しい。
そういう金沢に住んで居たい。

中学2年。そのほとんどの時間をともに過ごした友がいる。
放課後休日問わず家を行き来していた。
遊び盛りで彼の家がどんな仕事をしているかなど全く無頓着に大きい家の彼の部屋へ直行して時を過ごした。
ある日、その家の奥の部屋にいくことがあった。
どうしてそうなったかは覚えてはいないが、薄暗い割と広い廊下を進んだ大きな襖の部屋だったように思う。
彼が襖を開けたとたんに目を覆った朱壁。
金沢の商家や町家には朱壁の座敷を持つ家はあったが、これほどの朱壁の部屋は見たことがなかった。
その奥の間の群青の青も垣間見えた。群青壁のそんな大座敷があることに驚いた。
いつも傍にいる友がそうした家に生を受けていたとは終ぞ思ったことが無かった。
別の話になるが、ある同級生の親友からお茶を嗜む訳でもないのに棗の注文があった。
そして、「前金は幾らほど、、、。」と尋ねられ驚いた。
親から職人にものを頼む時は3分の1ほどは前金を払うものだということは以前から聞いているが、
どれくらい払えばよいのかわからないので、、。と続ける。
「いや、前金もらって作ってないし。」と答えるとそれで頼んでよいのかと言う。
私も祖父や両親から聞いてはいるし、そうしている姿も見ているが、世代も変わり時代も変っている。
前金は有難い話でもあるが荷が重くもあり貰った機会はなかったが、
幼馴染みの、それも仕事や趣味が格別その向きでもない友の言葉に驚いた。
思えば、昔から彼の家の玄関には金沢の誰もが知る高名な漆芸家の衝立がある。
友曰く、「やっぱり、いいものはいいし、何かいいもの家に欲しいし。何かないとね。両親も好きやし。」
ああ、そうなのか、と同い年の言葉に金沢を気付かされる。
今でも、「すぐにお支払いします。親からもそう聞かされていますし。」と仰る方も少なくはない。
金沢のひとは資産を3分割すると言われていた。
無論、資産家や旦那衆でのことだが、不動産と動産と道具とに三等分する知恵。
道具というのは、美術品だったり、茶の湯や宴席の道具であったりだが、資産としての価値を持ち続け得るものであり、
それと家宝とするものとが「お」を付けられ、お道具となり、「お蔵」に入るものである。
色々と名品や良いもの、面白いものをお持ちのかたを「お蔵が深い」とも言ったりする。
お蔵の深いその奥には何があるのだろう。
代替わりに持ち主からも知られずに何か眠っているかもしれない。
お侍と旦那衆が金沢の文化と言われる中心を担ってきた。
百万石の前田家と家臣、町方旦那衆どちらの車輪も外せない。
何かの両輪とよく言うが、金沢にはまだ他にも車輪があるように思う。
金沢の美術館でさほど地元に縁のない洋画家の回顧展が開かれた。
その初日、会場で町内の顔見知りの4名の方と顔を合わせた。
町内町会と言っても北國街道沿いの130戸程。
開会式直後だから、それぞれ一番に見に来たということになる。
ご近所のかたの葬儀に出る。自動車製造会社の定年を過ぎ古希もだいぶ超えられてれた。
兄や妹とも大変縁のあった方だが、通夜で謡が大変好きでお上手であられたと初めて知った。
兄妹も然程とは知らなかったという。
隣の班の建具屋さんも文化に興味が深いい分かってはいたが、謡を教えておいでるとは知らなかった。
蒔絵師は謡本の帳崩しを(謡曲を書いた本を分解して)金蒔絵の研ぎ汁を拭うのに使っている。

自宅前の雪すかしをしていると、不意に思い掛けない知人が声をかけてくる。
その方のお住まいは随分離れて用事でもない限りここを通ることもないはずだ。
何処へ と尋ねると、この少し先の小唄の師匠のところへ通っているという。
この町内に小唄の師匠さんがおいでるとは知らなかった。
町歌を持つほどの町会なのだが、小唄の師匠さんのことは知らぬ方がほとんどだろう。
今では町並み保存地区のこの街道沿いでも町家の造りの家がほとんど姿を消した。
この辺りは鰻の寝床と呼ばれるように奥に細長い家屋が隙間なく連なる。
道も曲がっているので、寝床も捩れたり短かったりする。
何かの拍子にある家の奥庭や中庭の立派な木や灯籠が垣間見え驚いたこともある。
きっとあるだろう家は、この界隈にまだある。
金沢の街を歩くとあちこちにある。
ここら辺りは犀川の南口、職人たちが沢山居た。浅野川の北口も塗師が多かった。
今でも金箔関係は浅野川の北口。友禅川流しもある。
城下、両方の川の外側には、前田家の治める前から住む地の民の多い所。
下職も含め職人たちの多くは地の民だったのだろう。
戦国の世100年ほど「百姓の持ちたる国」としてあった金沢。
職人は独立独歩の気概高く、同業他者の生業より独自の制作に打ち込む人も多かった。
根気もある。心根もある。
いいものにも接し自身の中に生きている。
職商人(しょくあきんど)も多かった。自分で作って自分で売る人だ。
注文があったからそうなのか、作っても売れないからそうなのかはニワトリと卵。
金沢は地の利も手伝って本人の意識に関わらず食い道楽かも知れない。
見た目も味のうち、器がなんでも良いわけではない。
その食と場にあった器で食したい。港なら時に素手でもいい。
その港でも九谷で食べたい場もある。
正月には、蒔絵のお重におせちを詰め、
婚礼には、鯛の唐蒸し腹合わせを九谷色絵大皿に盛り謡《高砂》の一節がある。
治部煮もあり、専用の形の治部煮椀だってある。

そして金沢のひとは着道楽とも言われる。
婚礼時持参の桐箪笥を埋める着物をご近所さんに披露されることが通例となれば、
当事者ならずとも皆、着物の目利きとなる。
持参の蒔絵のお重で配り物をすれば、受けるほうも塗り蒔絵の目利きとなろうというものだ。
金沢は気付かぬうちに目利きになる街だ。
食べることも、着ることも単に鑑賞者ではいられない。
器は使う。着物は袖を通す。
娘や嫁の婚儀には着物や蒔絵のお重を持たせ、受けねばならない。
持たせる方もどうしよう。受けるほうもどう受けよう。
その価値を解らねば失礼にあたるし、此方が誂える着物などもあるだろう。
持たせる受ける、双方に目が必要だ。
全ては使うという洗礼をうける当事者にならねばならない。
今ではそういうことは無い。期待もしないし、その気の重さからも解放されてすっきりした。
ただ、そういう時代を経て「いいもの」という美意識の洗練と共有がなされて来ての
今の金沢がある。
外からは見えない 金沢。