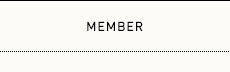| 佐無田 |
単純に言うと「きれいな建築」と「工芸建築」の違いはなんなのか? |
| 秋元 |
工芸建築はより依頼主の身体感覚に寄り添ったものだと思う。いまの建築は白々しい。ものすごくファンクショナルなダイニングがあってシンクもテーブルもすごい。しかしそれは別に“わたし”じゃなくてもよい。年収やライフスタイルをどんなに具体化しても自分には到達されず、抽象的なわたしが描かれている。自分らしいと思っても徹底的に抽象化される。むかしの人がもっていたモノとヒトとの関係は、いちど近代を通った人間は昔の感覚には戻れない。中世のようなモノとヒトとの関係がぴったりいくところには戻れない。 |
| 宮川 |
その関係をすこしでもブレイクスルーしてやろうというのが工芸建築? |
| 秋元 |
女性には誤解されてしまうかもしれないかけど、生でセックスがもうできないように、コンドームがあろうがなかろうが、どこかで情報化されてしまっている。いまの人はセックスをしながら 自分の体のなかに情報がインプットされていて、生々しいリアルには金輪際たどり着けない。なぜかというと文明をもったからです。それがものすごく高度化してしまった。好きになったらつける・つけないではなく、生で女性の中に入れるとしても決して生身なんてありえない。それは文明化されているからです。 |
| 宮川 |
例えがあれですけど、よくわかる(笑)。 |
| 秋元 |
いま佐無田さんが「きれいな建築」と言ったけど、内田さんもこの前「この写真きれい」って言ってたでしょ。それは圧倒的に加工されている。いわばだまされている。 自分のものだと思っても、作り手は内田さんや佐無田さんのためにつくったわけではなく、だいたいこんなものだろうと思ってつくっている。誰のためのきれいさとか快適さなのかはわからない。標準的な人間はいない。 |
| 小津 |
できあがってアッセンブルされた住宅はクライアントのためだけど、それを構成しているあらゆるパーツは大量製品ですね。 |
| 佐無田 |
大量製品ということではそうかもしれないけど、建築家も精神の面ではそういうものをつくろうと試みている。ただ、やはり工芸建築の工芸をフューチャーすると、工芸が培ってきた技能をどこで活かすのか。いまの話は精神論に聞こえるが、工芸の技術や技能をどう具体的に使うのか、工芸品をつくっている人たちの実際の仕事はどうなるんだろう? |
| 本山 |
わたしがこの会議に最初に参加したとき、工芸作家やギャラリーがどういうかたちで工芸建築に関われるかわからなかった。工芸は最初に素材があって、素材にどういう発想を落し込むかによって造形をつくってきた。しかし発想があって、その後に素材感がついてくるのは現代アート的です。工芸建築のアプローチとしては、発想があって素材が後からついてくるとすれば、具体的に作家やギャラリーはどうやって取り組むべきかって今は考えています。 |
| 秋元 |
たとえば、目に見えるかたちで100%工芸建築を満たしているものはあるかというと、姿勢としてはピーター・ズンドーのようなものや、自分がやっていた直島の家プロジェクトがある。それは精神論もふくめてですね。工芸建築を具現化したものは何かというとわからないけど。 |
| 小津 |
ピーター・ズンドーの作品はディテールを見ても、できあがった作品がわかる。断片が全体と一緒になっている。 |
| 秋元 |
工芸をつくっている人たちを、その人たちの作品から入ると見誤る。コンテキスト主義においては、作品はその人の一面でしかない。ソロで歌うからソロのような歌い方をしているので、 コーラスだと全然違うかもしれない。だからリソース化したほうがよいと思ってるんです。アウトプットした作品から作品を類推したらいけない。 |
| 宮下 |
工芸は引き出しをたくさんもっている。工芸家の人たちの活躍の場はきっとある。 |
| 秋元 |
いまの人間国宝の先生たちは過去の技術をさぞ継承しているように思えるけど、あの人たちが受け継いでいるものはひとつ。江戸時代に数多あった技法のたったひとつを継承しているにすぎない。おおかたはなくなっている。人間国宝の制度が生きていた時代もあったけど、あの人たちは欺瞞のなかで工芸的芸術を背負わされているところもあるんです。たとえば漆のように分業化されているもののなかで、ひとりの松田権六の作品が漆のすべてを体現することはありえない。作家によって芸術が保証されるという、近代的な美術の価値観のなかに工芸をおしこめただけ。実際は何人も関わっている。一人じゃできないです。 |
| 佐無田 |
総合的なものをつくろうとする営みのなかから、個々の要素である工芸を昇華するような建築ということですか。 |
| 浦 |
これは視座のとりかたの話になるんだけど、中村卓夫さんの家を見に行ったら、内藤廣というとても有名な建築家に設計を依頼したという。中村さんはよい手すりが既製品にはないので自分でつくったり、自分でOSDという高級ではない素材に漆を塗ったりして、そのバランスを見ながら施しをしていったわけです。彼は「これまでの座敷生活から西洋様式に変わっているのに工芸作家は気づいていないことが課題だ」と認識していた。だから彼の家のなかにはひとつも和室がない。その視座のとり方と彼の作品はつながっている。そのことに気づくのは大事なことです。日本建築は大工さんがつくったけど、木造で欧州とちがって仮設的なつくりが多い。同じ空間でバリエーションも少なく、畳1枚のモジュールからつくられている。日本の工芸作品は空間の置かれる場所がだいたい想像できる。欧州では空間のバリエーションが古くから多様だったんじゃないかな。日本は様式主義にはまって個々の発想が弱い。そこは日本の作家の課題です。 |
| 秋元 |
もっと言うと、工芸が近代化する過程では、どういう文脈に置かれるのがよいかはいっさい考えられていない。皿や壺のかたちになってるだけで、それを置ける家はどこにもない。中村卓夫さんがなぜ建築を大事に考えたかというと、自分がつくりだす工芸的なオブジェクトは、なにがしかのコンテキストや文脈が住空間に必要で、もはや日本家屋ではなくモダンな建築空間のなかで実験するしかない、と。そのための場として住宅をつくった。とても大事なことだと思う。 |
| 宮川 |
そういう発想をもった作家はあまりいないんですか。 |
| 秋元 |
あたえられた役割を果たすことにみんな必死になってる。たとえば展覧会に出すこととか、美術館に展示されることとか。伝統工芸の人はそのなかで日夜何をしているかというと、隣の人よりもより部分のディテールをしっかり出してやろうとか、重箱の隅をつついているようなもの。それ自体は技術でもなんでもなく、捨ててもよいこと。 |