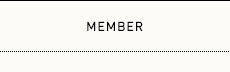東日本大震災の発生から2年半になろうとしています。日本環境会議という団体のシンポジウムの開催にあわせて、宮城県南三陸町から福島県南相馬市までを回ってきました。
正直、金沢に暮らしていると、震災の風化を感じざるを得ません。原発事故にいたっては(政府の収束宣言とは裏腹に)まだ汚染を出し続けている状況にもかかわらず、被災地から遠く離れて暮らす人の心のなかからは、震災の景色はだいぶ薄らいでしまっているようです。しかし、現地に立ってみれば、まだ広大な被災地が更地化されている作業中であったり、除染中であったり、仮設住宅での暮らしが続いていたりと、2年半経った現在も復旧さえままならず、災害がいまなお続いていることを強く実感します。
さて、日本環境会議のシンポジウムから、私が心に残ったことを1つ紹介します。
「震災と復興――災害弱者の人権と環境権をどう守るか」と題されたシンポジウムで、被災者支援、災害と女性、外国人女性、というテーマの3つの報告がありました。3報告に共通していたことは、被害は社会的弱者に集中すると言われてきたけれど、そうした社会的に厳しい状況に置かれたいわばマイノリティの人たちに、単に目を向けるだけでなく、彼らは地域の人材であり、資源であるとして、積極的に位置づけていこうとする視点でした。
南三陸町保健福祉課で被災者生活支援センターの活動を紹介された本間照雄さんは、東北大学員で博士号をとられて専門研究員にもなっている方ですが、実践的な支援政策に取り組みながら、それらを理論的にも整理されていて、たいへん参考になりました。
被災者生活支援センターの制度設計は、簡単に言えば、被災者でもある町民を生活支援員として雇用し(緊急雇用創出事業)、専門の有資格支援員と被災者の間に入ってもらい、コミュニティの社会資源を活かした地域の見守り活動の裾野を拡げる取組みです。とくに滞在型支援員は、高齢で出不精の人をあえて選び、彼らの地縁力を発揮してもらうやり方をしています。実地だけでなく座学(研修会)での教育訓練もされています。
これは、たとえ生活支援の素人でも、町民は、震災で生き残った意味を考え、町に貢献したいと思っており、被災者と同じ目線で心の痛みや生活の苦しさにいちばん寄り添える適材であるという発想によります。町民の手で被災者支援を行いながら、同時に町の復興を支える人材づくりもする仕組みで、津波で多数の職員が流されてしまった行政の資源不足を補う工夫でもあります。
この話は、震災復興にとどまらず、過疎地域をはじめ、これからの地域福祉を考える上で、たいへん示唆的でした。これまでの福祉国家の思想では、ナショナル・ミニマム(国民1人あたり最低限同じ水準の福祉を保障されるべきだという基準)により、所得の格差を減らすための援助の発想を基本にしていましたが、被援助者が多数の社会となれば、もはや財政的に成り立ちません。これに対して、地域福祉は、社会的弱者は地域の人材であり資源であるという発想、つまりエンパワーメント(empowerment)が基本であるという原則を、この事例は示唆しています。
ただし注意すべきは、これは自助自立を主張する「小さな政府」論とは違うということです。社会的に弱い立場の人が社会的な役割を得て協働する仕組みづくりこそが行政の役割になるという「市民自治」論だと、本間さんは言います。強調されていたことは、「雇用」を創出するのではなく、南三陸町民としての「社会的役割」を創る、ということでした。
「福祉」のあり方とともに、「仕事」のあり方についても、考えさせられます。戦後日本の福祉は、再分配よりも、雇用と所得の基盤となる「産業」の立地を誘導する産業立地アプローチを重視してきました。この政策思想はいまだに根強く、震災復興でも過疎地域再生でも、まず「産業」の振興に焦点が当たります。仕事場がなければ、地域から人が出て行ってしまうからです。ところがその地域社会を支えるための産業振興策が、宮城県の「水産業復興特区」のように、共同体の秩序を壊すとして、地域の社会的対立を生んでいるのは、皮肉としかいいようがありません。
これとは対照的に、南三陸町の事例で示されたことは、「仕事」とは、「雇用」ではなく、「社会的役割」だという視点でした。人はお金が必要だから働くのか。それもあるが、もっと個々人が求めていることは、社会の中で必要とされる役割や居場所なのではないか。これは、高齢者福祉から若者支援、ひいては地域づくり全般を貫く共通項かもしれません。
同じシンポジウムで話された佐々木アメリアさんの報告によれば、南三陸の「外国人妻」は、震災前は「家政婦」的地位に甘んじていたのが、震災をきっかけに日本人家族よりも果敢に行動して周りの見る目が変わり、さらに日本語の勉強を兼ねた介護士の資格の勉強やパソコン教室などに集って、自分たちが町にとって貴重な人材たることを示そうと、たいへんパワフルだそうです。日本人はすぐに国を頼ろうとするが、フィリピン人はそんなこと考えたこともない、といわれると納得で、この異文化効果は被災地では効果的だったでしょう。
このように、地域社会の現場では、たしかに「仕事」が求められているのですが、それは会社が立てられて何人雇用されるかという数字的なものではなく、むしろ1人1人が役割を見いだして行動する地域の社会的な関係性であって、そのような社会的役割に報酬が伴うような経済的な仕組みこそが求められていることがわかります。
東日本大震災は、戦後日本60年の転換点だとよく言われます。しかし、何が変わったのか、変わろうとしているのかは、まだはっきりとしていません。ともかく、被災地の再生の過程が示しているのは、震災被害からの復興の課題だけでなく、実は日本社会を先取りするような先鋭化した地域の問題に直面した姿であり、そこでは、戦後日本の骨格とされてきた「福祉」や「仕事」のあり方の根本的な発想の転換を含む、ポスト福祉国家、ポスト雇用社会の地域的な実験が試みられているのだと、今回あらためて感じた次第です。